哲学者としての三浦梅園
その6:役に立つもの立たないもの
今まで私は梅園の思索のあり様を絡めながら哲学というものがどのような知的
歩みであるかを語ってきました。〈自然=存在〉そのものへの懐疑、そして常識
的世界への反省的態度などの根源への問いが哲学の出発点であり、そこから宗教
や科学などの人間の他の文化的営みとの関わりを明らかにしてきたわけです。し
かし、このように哲学についておぼろげながらイメ−ジが出来上がったにせよ、
この文章を読む人の中にはまだ不満を持つ人も少なくないと思います。つまり、
「だから哲学は一体なんだ」、もっと端的に言うなら ば「だからといって哲学
は何の役に立つのか」という疑問が残されているというわけで す。しかし、こ
のような疑問に対して、私は哲学そのものが「役に立つ」という有用性の物差し
で計ることができない、むしろそのような物事の基準を越えていると答える以外
仕方がありません。これは、哲学が根源的なものを希求する学であり、「役に立
つもの」を成り立たしめている前提を探究する学問である以上、当然といえば当
然のことであるでしょう。もし哲学が必要であると言うならば、まさに「役に立
つ」ことに先立つものを見出す学問が必要であるからだということになります。
梅園の懐疑の根源性についてはすでに幾度か触れましたが、これは彼独自のも
のというよりも、哲学するものに特徴的なことだと私は思います。私自身の話を
して大変恐縮ですけれども、私も小さい頃に梅園と同じような世界の根源に対す
る疑問を持ったことがあります。そのまず第一は「私たちを含めた世界そのもの
は何のためにあるのか」というものでした。「僕達はテストの点数を上げるため
とか、よい生活をするために多くの努力を払っているけれども、それは結局本当
は何のために行なわれているのか」というわけです。キリスト教徒の人達ならば
それは神の栄光のためということになるかもしれませんが、私はこの問いには答
えがないと思いました。結局は、自分自身が「よい」と感じるものが「○○のた
め」という目的を生み出しているのであり、おぼろげながら、世界そのものを越
えて「世界は○○のためにある」と理屈づけるのは無意味であると感じたので
す。今思うに、この問いは人間の宗教的関心を明らかにするものであり、社会的
常識、そしてそれによって正当化される多くの目的の限界をはっきりさせるため
の答えのない問いだったといえるでしょう。
第2の問いは「この世界のすべての物体は無限に分割されうるのではないか」
という問いでした。「今私が文章を書いている鉛筆をどんどん半分に切って行っ
ても、結局終りはないのではないか? そして、無限に小さな物体が成り立つ以
上、無限に小さな無限に 多様な世界がこの鉛筆の中にあってもおかしくないの
ではないか? 否、相手は無限なのだからきっとあるにちがいない」と思ったわ
けです。この問いも先の問いと同じく世界の根源に対する問いであり、答えは出
ないのですが、先の問いが人間の宗教的関心に関わるのに対し、これは人間の科
学的関心を明らかにするもののように思えます。確かに科学は常に限界づけられ
た一定の知識しか与えませんが、人間が科学的関心を持ち続けていられるのはこ
のような無限の可能性を持つ〈自然=存在〉への知的憧憬があるからだと思いま
す。
常識的な世界に安住している人達はこのような宗教的関心や知的憧憬を意識す
ることはほとんどありません。これは日常私たちが社会によって暗黙に決められ
た〈役に立つものと−役に立たないもの〉の基準に従って、より根源的なものに
目を向ける必要を感じないからです。とにかく、人間として何をなすべきか何を
目指すべきかは常識という社会的規範の中に明らかにされているのであり、実際
のところ、たいていの人々はその時々の仕事に追われて生活を送っているのが実
情ではないかと思います。そのような忙しい人々にとって哲学とは「役に立たな
いもの」であるにとどまらず「有害なもの」と見なされること もしばしばで す。しかし、よく落ち着いて考えるのならば、社会的常識の提示するこの
「有用性」というものがどれだけの妥当性を持つのか疑問です。確かに、一定の目的
を持ち、その目的に向って努力することはいいことのように思われがちですが、
その目的そのものが常に正しいとは限らないのも真実です。かつて日本人は正義
の名の下に大陸に進出しましたが、それは結局侵略にほかならず、多くの日本人
の努力はより多くのアジアの人々の恨みを生む結果となってしまいました。今日
でも、一番初めのところで述べた金融スキャンダルのように、個人の血のにじむ
ような努力が結局犯罪となってしまう例は決して少なくはありません。このよう
な歪んだ常識的社会というものは、あたかも舵を欠いた船のようなものであっ
て、このうえもなく危険なものだと私は思います。現代社会、殊に今の日本の現
実は、経済大国という繁栄の大船に乗っていながらも、まるで海図も舵もない状
態にあるように思えてなりません。この大船の中で人々は皆あわただしく饗宴の
準備に明け暮れていますが、だれも忙しくて船のうえに出てこの船そのものがど
こへ向かっているのか、どこに行くべきなのかを考えようとしません。この船の
中では饗宴の準備をすることが「役に立つ」と見なされても、船のうえに立つこ
とはむしろ有害なことと見なされているわけです。
このような常識的世界に甘んじ、みずからを「役に立つ」人間だと思っている
人々は、あの釈迦の掌のうえで飛び回った孫悟空のような人間だと私は考えま
す。いかに自分が社会的に有用であると思っても、それは〈役に立つもの−役に
たたないもの〉の前提の上での話であって、ただそれだけのことでしかないので
す。私はこの西遊記の話に出てくる釈迦の掌を〈自然=存在〉の理法であると思
います。つまり、常識的世界に(梅園の言葉を借りれば)馴染んだ人々にはこの
釈迦の掌は見えないけれども、いかなる人々もこの外に出ることは出来ないとい
うわけです。
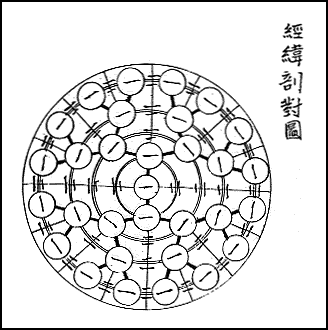 梅園の玄語図はこの理法の世界を哲学者の立場から見事に図像化したものでは
ないかと私は考えています。すでに仏教の伝統の中ではマンダラが宇宙の理法を象徴する
ものとして一般化しているのですが、哲学の立場から論理的に世界のあり方を図像化して
いるのは玄語図以外にはないように思えます。この図の基本的パタ−ンは「一即一一、一
一即一」の単純な相即の論理によっていますが、その表現する世界は無限の広がりと多様
性を持っています。「一即一一、一一即一」の論理の組み合わせと、この<一>部分に現実
世界のあり様を見出すことによって、〈自然=存在〉の論理的単純性と現実的多様性とが
見事に表現されていると言っても過言ではないと思います。確かに、具体的事柄
について彼の玄語図は索強付会の部分も多いのですが、単純な論理が多様な世界
を裏付けているという哲学的確信を、彼は図を用いることによって明かにしてい
るように思えます。いかに具体的で偶然的なもののように見えても、その中には
必然的な理法が働いているのであって、釈迦の掌のようにだれもそこから逃れる
ことは出来ないのです。
梅園の玄語図はこの理法の世界を哲学者の立場から見事に図像化したものでは
ないかと私は考えています。すでに仏教の伝統の中ではマンダラが宇宙の理法を象徴する
ものとして一般化しているのですが、哲学の立場から論理的に世界のあり方を図像化して
いるのは玄語図以外にはないように思えます。この図の基本的パタ−ンは「一即一一、一
一即一」の単純な相即の論理によっていますが、その表現する世界は無限の広がりと多様
性を持っています。「一即一一、一一即一」の論理の組み合わせと、この<一>部分に現実
世界のあり様を見出すことによって、〈自然=存在〉の論理的単純性と現実的多様性とが
見事に表現されていると言っても過言ではないと思います。確かに、具体的事柄
について彼の玄語図は索強付会の部分も多いのですが、単純な論理が多様な世界
を裏付けているという哲学的確信を、彼は図を用いることによって明かにしてい
るように思えます。いかに具体的で偶然的なもののように見えても、その中には
必然的な理法が働いているのであって、釈迦の掌のようにだれもそこから逃れる
ことは出来ないのです。
自然にしても社会にしても、それらははじめから今あるような姿であったでは
なく、またこのまま今と同じような形で固定的に維持されるわけではありませ
ん。確かに「玄なる」理法とも言うべき条理そのものは変化しないとしても、そ
れの織り成す世界の現実的姿は、仏教の説くように、無常で移ろい行くもので
す。この〈役に立つ−立たない〉という常識的判断もそのようなものであり、常
により高い立場から反省され批判されなくてはならないといえるでしょう。そし
て、その反省や批判の地歩を築くのが哲学なのであり、更にそのそのきっかけを
与えてくれるのが根源的なものへの懐疑というわけです。それ故、哲学において
はすでに常識によって決められたことをそのまま正しいことと認めるわけには行
きません。たとえ、認めるにしても、何故そうなるかということをその事柄のプ
ロセスに従って理解する必要があります。つまり、知識にせよ何にせよ、与えら
れるものをすでにでき上がったもの、完成したものとしてそのまま受け入れるの
ではなく、それなりの理由を認めたうえで受け入れるのが哲学の立場であるとい
うわけです。
しかし、忙しい現実のことを考えれば、日常世界が常識に依存していることを
責めるわ けには行かないでしょう。けれども、学問の領域でさえもその傾向が
著しいのは問題で す。日本の学問は今まで、中国にせよヨ−ロッパにせよ、先
行する国々の成果を受け入れることによって成長して来ましたが、まさにこのた
めに学問の結果だけをその成立のプロセ スから切り離して取り入れて来たと言
うことができるのではないかと思います。一般 に、日本人が応用的問題を解く
ことに秀でているが、その問いそのものを、特により根源的、本質的問いそのも
のを見出す能力に欠けているとよく言われます。つまり、日本人には学問的常識
を覆す問いを発し、その問いから新しい学問のあり方を見出す能力が弱いという
わけですが、これは確かに認めざるをえない事実だと思います。
殊に、哲学という学問においてはこの問いを発する能力が決定的な意義を持つ
ことについてはすでに何度か述べてきました。哲学は科学とは違って答えそのも
のが成り立たない問いであってもそれが根源的なものに私たちの意識を向けると
いう点で重要だったわけです。この意味で私は三浦梅園を哲学者であると確信す
ると同時に、彼が日本の知的伝統の中で例外的な存在であったことを感じざるを
えません。しかし、だからこそ日本人にとって日本人である梅園を見直す事は大
きな価値があると思います。梅園研究の第一人者であった三枝博音氏は、すでに
30年以上前にこのことをはっきり自覚していたようです。氏は、岩波文庫「三
浦梅園集」の解説の冒頭で次のように述べています。
もし誰かが、ほんとうに哲学の精神でもってつらぬかれているような書物を明
治以前のものから取り出せといわれるなら、私は躊躇するところなく梅園のこの書
を挙げようと思う。この書(多賀墨郷君にこたふる書)は手紙の形で書かれて居
り、分量も多くはなく、文体において今日の読者には親しみがたい点があるでもあろ
う。しかし、それにもかかわらず日本の哲学思想史のなかで不朽の価値をもちつ
づけるものと思われる。なぜなら、人は真理を求めたいなら、学問的問に心せよと
いうことを、梅園はこの書において思索的に縷々書き綴っているからである。一般
に学問において、博学は貴ぶが、「問う」ことの意義の重要さを考えてみることは
しなかったわが国の思想家のなかで、梅園のような学者は稀れな存在だといわねば
ならない。彼が、問うということを中心にして、自分自身に投げかける問いこそ、
哲学の精神でなくてはならない。(岩波文庫「三浦梅園集」32P)
恐らく彼のいうこの哲学的精神こそ梅園の最大の魅力であり、当時も今も日本人
に一番求められているもののように思えます。
私はこのような哲学の営みを、人間の自らに対する良心のまなざしと考えてい
ます。というのも、これこそが常識に身をゆだねてしまうために生じる日常の危
険に人々の注意を向け、それを未然に防ぐことができるからです。日常の生活は
常識によって営まれているからこそ、人々はいたずらに迷うことなく、また混乱
することなく生活を営むことができるのも確かです。しかし、それですべてが良
いというわけでは決してなく、常識によって物事がうまく運ばれるからこそ、む
しろそれによる危険も大きいのです。慣れというものは便利ですが、常なるもの
にあまりも慣れ過ぎてしまうことは、常ならざるものに対して無防備になること
を意味します。このように日常の社会的な生活においては、むしろ常識に従うこ
とが物事の基準ですけれども、もし人々が個人として一人ひとりの醒めた目でそ
れを問い返す努力を怠るのであるならば、その社会全体が、そして我々の日常的
生活そのものが歪んでいくのを避けることはできないでしょう。それ故に、常識
はより高い良識の立場からの反省を必要とするのであり、その良識がまさに良識
であるのは、人間が一人ひとりその内に持っている良心の支えがあるからだと言
えるでしょう。この意味で、哲学とは、その良識を育む学として、人間の社会と
自然、そして自分自身に対する誠実なる良心の現れなのであり、常なるものに安
住しがちな人々の怠惰からそれらを守る砦なのです。
[←戻る]
[三浦梅園のこと]
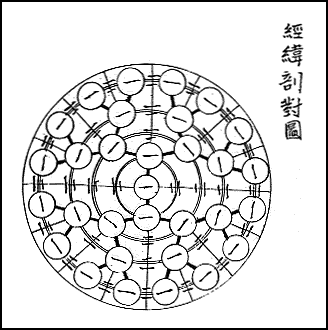 梅園の玄語図はこの理法の世界を哲学者の立場から見事に図像化したものでは
ないかと私は考えています。すでに仏教の伝統の中ではマンダラが宇宙の理法を象徴する
ものとして一般化しているのですが、哲学の立場から論理的に世界のあり方を図像化して
いるのは玄語図以外にはないように思えます。この図の基本的パタ−ンは「一即一一、一
一即一」の単純な相即の論理によっていますが、その表現する世界は無限の広がりと多様
性を持っています。「一即一一、一一即一」の論理の組み合わせと、この<一>部分に現実
世界のあり様を見出すことによって、〈自然=存在〉の論理的単純性と現実的多様性とが
見事に表現されていると言っても過言ではないと思います。確かに、具体的事柄
について彼の玄語図は索強付会の部分も多いのですが、単純な論理が多様な世界
を裏付けているという哲学的確信を、彼は図を用いることによって明かにしてい
るように思えます。いかに具体的で偶然的なもののように見えても、その中には
必然的な理法が働いているのであって、釈迦の掌のようにだれもそこから逃れる
ことは出来ないのです。
梅園の玄語図はこの理法の世界を哲学者の立場から見事に図像化したものでは
ないかと私は考えています。すでに仏教の伝統の中ではマンダラが宇宙の理法を象徴する
ものとして一般化しているのですが、哲学の立場から論理的に世界のあり方を図像化して
いるのは玄語図以外にはないように思えます。この図の基本的パタ−ンは「一即一一、一
一即一」の単純な相即の論理によっていますが、その表現する世界は無限の広がりと多様
性を持っています。「一即一一、一一即一」の論理の組み合わせと、この<一>部分に現実
世界のあり様を見出すことによって、〈自然=存在〉の論理的単純性と現実的多様性とが
見事に表現されていると言っても過言ではないと思います。確かに、具体的事柄
について彼の玄語図は索強付会の部分も多いのですが、単純な論理が多様な世界
を裏付けているという哲学的確信を、彼は図を用いることによって明かにしてい
るように思えます。いかに具体的で偶然的なもののように見えても、その中には
必然的な理法が働いているのであって、釈迦の掌のようにだれもそこから逃れる
ことは出来ないのです。